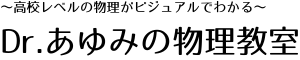現代の人間の生活には、電気が欠かせませんね。
冷蔵庫、テレビ、洗濯機、パソコン、スマートフォンなどなど・・・。
電化製品があるから、便利な生活を営むことができますよね。
電化製品は、充電したりコンセントにつないだりして使います。
ですから、電気を通しやすい物質でできているはずですね。
でも、スマートフォンや冷蔵庫を触っても感電しないのはなぜでしょう?
それは、人間が触る部分を、電気を通しにくい物質でカバーしているからなのですね。
身の周りには大きく分けて、「電気を通しやすい物質」と「電気を通しにくい物質」があります。
小中学校の理科でも、「金属は電気をよく通す!」とか「ゴムは電気を通さない!」とか調べましたね。
科学の世界では、「電気を通しやすい物質」を『導体(どうたい)』、「電気を通しにくい物質」を『不導体(ふどうたい)』と言いますよ。
ところで、電気を「通しやすい」と「通しにくい」物質って、何が違うのでしょうか?
また、物質をつくっている原子(げんし)の構造まで戻ってみましょうか。
原子は、正の電気を帯びた原子核(げんしかく)と負の電気を帯びた電子(でんし)でできています。
電気つながりで何か分かりそうですよ。
目次
導体と不導体
世の中のあらゆる物体は原子という小さな粒の集まりですね。
そして、原子は原子核と電子からできているのでした。
原子核は正の電気を、電子は負の電気を帯びていますよ。
静電気(せいでんき)の記事でお話したように、原子から電子がポコーンと1個飛び出すと、1価の陽イオンになりますね。
 図1 陽イオン
図1 陽イオン
実は、電子の離れやすさは、原子の種類によって違いますよ。
原子核と電子の結びつきが弱い場合、電子は離れやすいです。
反対に、原子核と電子が強く結びついた場合は、電子が離れられないわけです。
ここが、『導体』と『不導体』の違いを理解するポイントですよ。
ここから先は、陽イオンを●に+、電子を●に-で表しますね。
導体とは
銅やアルミニウムなどの金属のように、電気を通しやすい物質のことを『導体』と言います。
『伝導体(でんどうたい)』や『良導体(りょうどうたい)』と呼ぶこともありますよ。
電気をよく伝える、よく通す、という文字通りの意味なのですね。
導体の中にある原子核は、電子を引きつける力が弱いのです。
電子は、自由に導体の中を動き回っていますよ。
負の電気を帯びた電子が自由に動き回る=電気がよく通るという仕組みなのです。
ですから、導体は電気を通しやすいのです。
このように、導体の中を自由に動く電子を、『自由電子(じゆうでんし)』と言いますよ。
金属のような導体の中は、図2のイメージです。
規則正しく陽イオン(中心に原子核がある)が並ぶ間を、自由電子が自由自在に動き回っていますね。

図2 金属などの導体のイメージ
では、『不導体』の中の電子はどうなっているのでしょうか?
不導体とは
ゴムやガラス、紙、空気などのように、電気を通しにくい物質のことを『不導体』と言います。
『絶縁体(ぜつえんたい)』や『誘電体(ゆうでんたい)』と呼ぶこともありますよ。
電気を伝えにくい、通しにくい、ということを表しているんですね。
不導体の中にある原子核は、電子を引きつける力がとても強いのです。
それでは、電子は原子核の周りから自由に離れることができませんね。
ですから、不導体は電気を通しにくいのです。
ゴムのような不導体の中は、図3のような感じです。
電子は、陽イオン(中心に原子核がある)の周りから自由に離れることができませんね。

図3 ゴムなどの不導体のイメージ
つまり、導体と不導体の違いは、電子が自由に動けるか、原子核の周りくらいしか動けないかだけなんですね。
ちょうど、飼い主(原子核)と犬(電子)のようなイメージでしょうか。
導体の中では、犬はリードでつながれていないので、飼い主から離れて自由に走り回ります。
でも、不導体の中では、飼い主と犬はリードでつながれているので、犬は飼い主から離れられないわけですね。

図4 導体と不導体の中の原子核と電子
さて、『導体』と『不導体』について見てきましたが、もう一つ似たような言葉を聞いたことはありませんか?
そう、『半導体(はんどうたい)』です。
パソコンやスマートフォン、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、発光ダイオードなど色々な電化製品のセンサーなどに使われていますね。
「半」分は「導体」とは、どういうことなのでしょうか?
半導体とは
『半導体』は、その名の通り、導体と不導体の中間の性質を持っていますよ。
つまり、ある条件のときだけ電気を通します。
電気の通しやすさをコントロールできるわけですね。
代表的な半導体物質には、ゲルマニウム(元素記号Ge)、シリコン(元素記号Si)、ダイヤモンド(元素記号C)、セレン(元素記号Se)などがありますよ。
半導体に少しだけ不純物(ふじゅんぶつ)を入れると、電気が流れやすくなります。
このような半導体を、『不純物半導体』と言いますよ。
具体的なイメージは・・・、
物理基礎の範囲では説明が難しいので、物理分野で詳しく解説しますね。
それでは、理解度チェックテストで理解を深めましょう!
導体と不導体理解度チェックテスト
【問1】
次の文章中の( )を埋めよ。
金属などのように、電気を通しやすい物質を(ア)と言う。
それに対し、ガラスやゴムなどのように、電気を通しにくい物質を(イ)と言う。
(ア)が電気を通しやすいのは、物質の中で自由に(ウ)が動き回っているからである。
(イ)が電気を通しにくいのは、(ウ)が(エ)に強く引きつけられて(エ)の周りしか動くことができないからである。
(ア)と(イ)の間の性質を示すのが、(オ)であり、ある条件のときだけ電気を通す。
電気を通しやすくするために、(オ)にわずかな不純物を入れたものを(カ)と呼ぶ。
まとめ
今回は、導体と不導体、少しだけ半導体についてお話しました。
導体は、
- 金属などのように、電気を通しやすい物質
- 自由電子が自由自在に動き回っているので、電気を通しやすい
不導体は、
- ゴムなどのように、電気を通しにくい物質
- 電子が原子核の周りしか動けないので、電気を通しにくい
半導体は、
- 導体と不導体の中間の性質を持ち、ある条件のときだけ電気を通す
- わずかな不純物を入れると、電気が流れやすくなる
導体と不導体の中では、電子の動きがどのように違うのか、しっかり理解してくださいね。
次回は、導体の静電誘導と不導体の誘電分極についてお話しますね。
こちらへどうぞ。