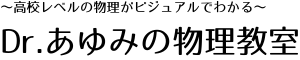物理を学んでいると、聞きなれない用語が出てきたり、日常生活で使うときとは意味が少し違う用語が出てきますよね。
物理で使われる用語は、意味がきっちりと決まっているんですよ。
なので、それぞれの用語をしっかりと理解すれば、問題文が読めるようになります。
例えば、『鉛直(えんちょく)』と『垂直(すいちょく)』。
何となくごっちゃにして使っていませんか?
『鉛直』は、力学分野の「鉛直投げ下ろし」や「鉛直投げ上げ」で使われています。
それから、重力の方向を「鉛直下向き」と言いますね。
でも、「垂直投げ下ろし」「垂直投げ上げ」「垂直下向き」とは言いません。
『垂直』と言えば、物体が接している面から受ける「垂直抗力(すいちょくこうりょく)」を思い浮かべる人も多いでしょう。
でも、「鉛直抗力」とは言いませんよね。
このように、『鉛直』と『垂直』は使い分けられていますが、その違いは分かりますか?
難しい違いではないので、ここではっきりと理解しておきましょうね。
目次
鉛直と垂直
『鉛直』と『垂直』の違いをざっくり言うと、こういうことです。
- 『鉛直』は重力の方向
- 『垂直』はある面や線に対して直角(90°)をなす方向
では、この意味についてもっと詳しく見ていきましょうね。
鉛直とは
最初に、『鉛直』と言えば「鉛直投げ下ろし」、「鉛直投げ上げ」、重力の向きである「鉛直下向き」がありますね、と言いました。
この3つの言葉には、全て重力がからんでいますよね。
そう、『鉛直』という言葉には、重力が関係あるんですよ。
正確に言うと、『鉛直』とは糸の先におもりをつるして静止したときに糸が向く方向、つまり重力が作用する方向のことです。
地面という水平面(すいへいめん)に対して直角をなす方向、でもありますね。

図1 鉛直方向
また、重力が作用する方向を示す直線のことを「鉛直線」と言いますよ。
鉛直線にそった下向きを「鉛直下向き」、上向きを「鉛直上向き」と言います。
なので、「鉛直投げ下ろし」「鉛直投げ上げ」という言葉から、鉛直線にそって下向きまたは上向きの運動であることがすぐ分かるわけですね。
ところで、『鉛直』という言葉にはなぜ金属の「鉛」が使われているのでしょう?
昔、土地の測量などで鉛直方向を正確に知りたいときは、鉛のおもりをつるした糸(鉛糸・えんし)を使って調べていたんですね。
そこから『鉛直』という言葉が生まれたと言われています。
次は、似ているようで違う『垂直』について見ていきましょう。
垂直とは
『垂直』とは、ある面や線に対して直角をなす方向のことでした。
数学でも習っていますから、知っている方も多いでしょう。
つまり、基準となる面や線は地面のような水平面とは限らず、壁のように直立した面や斜面でも良いわけですね。
なので、基準となる面や線によって、それと直角をなす垂直方向はありとあらゆる向きになるのです。

図2 垂直(青色の矢印)の例
『鉛直』は重力の作用する方向ただ1つに決まりますから、そこが垂直との大きな違いですね。
そして、地面という水平面に対する場合のみ、鉛直方向と垂直方向は同じ方向になります。
もし「垂直投げ下ろし」「垂直投げ上げ」と言ってしまうと、基準面が分からないので、「どこに向かって投げたの?」となってしまいますよ。
「垂直抗力」を考えるときに、いつも地面に対して垂直だと決めつけるのではなく、接している面が地面なのか壁なのか斜面なのか確認する理由も分かりますね。
ここで、『鉛直』と『垂直』の違いについてまとめておきましょう。
鉛直と垂直の違い
- 『鉛直』は重力が作用する方向で地面(水平面)に対し直角をなす方向
- 『垂直』はある面または線に対して直角をなす方向
- 基準面が地面(水平面)のときのみ鉛直方向と垂直方向は同じ方向

図3 鉛直と垂直
さて、『鉛直』の説明のところで「水平面」という言葉が出てきましたが、『水平』とは何でしょう?
『水平』についても少し見ておきましょう。
水平と平行
鉛直と水平
『水平』とは鉛直と直角をなす方向のことですね。
重力が作用する方向と直角になるわけですから、高校物理では平らな地面と考えて良いでしょう。
つまり、地面に対して平行(へいこう)でもあるわけですよ。
例えば、「地面の上に置かれた物体にかかる力を鉛直方向と水平方向に分力しなさい」という問題文を見たことありますよね。
『鉛直』と『水平』という言葉が使われていますから、「地面に対して直角」と「地面に対して平行」な2方向に分力しなさい、という意味なのです。

図4 鉛直方向と水平方向への分力
『鉛直』と『水平』はお互いに直角をなすペアなんですね。
そして、基準面は地面(水平面)と決まっています。
では、『垂直』にはペアはいないのでしょうか?
いえ、『平行』がありますよ。
垂直と平行
『平行』とはある面や線をどれだけ延長しても決して交わらないことです。
なので、ある面や線に対して『垂直』と『平行』である2方向、というのはお互いに直角をなす方向なんですね。
ただし、「〇〇に垂直な方向」「〇〇に平行な方向」と基準面をはっきりさせないとわけが分からなくなりますよ。

図5 色々な基準面に対する垂直方向と平行方向
基準面が地面(水平面)のときのみ、水平方向と平行方向は同じ方向になります。
『鉛直』と『垂直』の違い、『水平』や『平行』との関係は分かりましたか?
「直」や「平」という漢字が共通して使われているので、ごっちゃになりやすいのかもしれませんね。
最後に、英語ではどう書くのか見てみましょう。
英語ではどう書く?
科学分野で使う英語では、『鉛直』『水平』『垂直』『平行』をこのように使い分けます。
- 鉛直:vertical
- 水平:horizontal
- 垂直:perpendicular
- 平行:parallel
『鉛直』のverticalと『垂直』のperpendicularは全然似ていませんね。
これらの単語は、技術英語や科学論文でもよく出てきますから、覚えておくと便利ですよ。
まとめ
今回は、『鉛直』と『垂直』の意味と違いや、『水平』と『平行』との関係についてお話しました。
鉛直とは、
- 重力が作用する方向で地面(水平面)に対し直角をなす方向
垂直とは、
- ある面または線に対して直角をなす方向
水平とは、
- 重力の方向である鉛直方向に対して直角をなす方向
平行とは、
- ある面や線をどれだけ延長しても決して交わらないこと
用語の意味をきちんと理解しておけば、物理の説明や問題文に書かれていることが正しく分かるようになりますよ。
最初は面倒かもしれませんが、その都度しっかり覚えていきましょう。