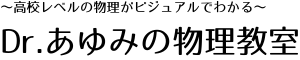『放射線(ほうしゃせん)』や『放射能(ほうしゃのう)』という言葉、一度は聞いたことがありますよね。
放射線って、一体どんなものなんでしょう?
目に見えないので、よく分かりませんね。
自然界には、昔から色々な放射線があったのです。
でも、人間が放射線の存在を知ったのは1890年代のこと。
ドイツの物理学者レントゲンが放射線の1種であるX(エックス)線を発見して、第1回ノーベル物理学賞(1901年)を受賞しました。
健康診断のレントゲンでおなじみですね。
それから、フランスの物理学者ベクレルがウラン鉱石から出ている放射線を発見し、キュリー夫妻がラジウムとポロニウムから放射線が出ていることを発見しました。
その後も大勢の科学者が放射線の研究を続けて、様々な測定や検査、治療などに応用されるようになったわけです。
ところで、『放射線』と『放射能』という言葉の区別はついていますか?
これから、『放射線』の種類や『放射能』との違いなどを詳しく見ていきましょう。
※スマートフォンで表が全て見られない場合は、横スクロールしてください。
目次
放射線と放射能
放射線の特徴
放射線が物質にぶつかったらどんなことが起こるのでしょう?
放射線には、電離作用(でんりさよう)と透過(とうか)という2つの特徴があるのです。
それぞれ、こういう働きをします。
| 電離作用 | 透過 |
|
放射線が物質を通過するときに、持っているエネルギーを原子に与え、電子をはじき出す(「電」子を「離」す)働き
|
物質を通り抜ける性質
|
煙を探知すると警報が鳴る煙探知機は、電離作用を使って開発されたんですよ。
病院のX線撮影は、透過作用を利用していますね。
電離作用や透過力の強さは、放射線の種類によって変わりますよ。
続いて、放射線の種類について見ていきましょう。
放射線の種類と正体
放射線には、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線、X線、中性子線などの種類があるんですよ。
ここでは、α線、β線、γ線について見ていきますね。
それぞれの正体や電離作用と透過力の強さは、こうなっています。
α線
α線の正体は、高速で流れるヘリウム原子核\(_{2}^{4}\rm{He}\)(α粒子)です。
ヘリウムの原子番号は2なので、陽子を2つ持っていますね。
ですから、α線は+2e [C](クーロン)の電荷を持っているわけです。
α線は一番大きさが大きくて電荷も大きいので、電離作用は最も強いです。
電離作用が強いほど自身のエネルギーを急速に失うので、透過力は最も弱く、紙一枚で止まります。
β線
β線の正体は、高速で流れる電子です。
ですから、β線は-e [C]の電荷を持っているわけですね。
β線の電離作用と透過力は、α線とγ線の中間くらいになります。
アルミニウムなどの薄い金属板で止まりますよ。
γ線
γ線の正体は、非常に波長が短い電磁波です。
電荷を持たないので、電離作用は最も弱いのですね。
透過力は最も強く、鉛や鉄の厚い板で止められます。

図1 α線、β線、γ線の透過力
α線は紙一枚で止まりますが、その紙は電離作用によりボロボロに破壊されてしまうのです。
γ線はコンクリートの壁を何mも透過しますが、コンクリートはほぼ無傷なんですね。
α線、β線、γ線の特徴をまとめておきましょう。
| 正体 | 電荷 | 電離作用 | 透過力 | ||
| α線 | ヘリウム 原子核 |
+2e | 強 | 弱 | 紙一枚で止まる |
| β線 | 電子 | -e | 中 | 中 | 薄い金属板で止まる |
| γ線 | 電磁波 | 0 | 弱 | 強 | 鉛や鉄の厚い板で止まる |
次は、「放射線」と「放射能」の違いについて見ていきましょう。
放射線と放射能
ウランやラジウムといった原子は、何もしなくても勝手に放射線を出してしまうのです。
このように、自然に放射線を出す性質のことを放射能と言いますよ。
そして、放射能を持つ物質を放射性物質、放射能を持つ原子を放射性原子、放射能を持つ同位体を放射性同位体(ラジオアイソトープ)と言います。
放射性物質が電球だとすると、放射能が光を出す能力、放射線が光にあたるわけですね。

図2 放射性物質と放射能と放射線の関係
さて、放射性物質は、どうして放射線を出すのでしょうね?
放射性崩壊と半減期
放射性物質の原子核はとても不安定なんですね。
例えば、\(_{\;{6}}^{14}\rm{C}\)という炭素の放射性同位体があります。
\(_{\;{6}}^{14}\rm{C}\)は不安定な構造なので、放射線を出して別の安定した物質になろうとするのです。
特に、原子番号が大きくなると原子核が大きくなりますね。
そうすると、核子を結びつけている核力よりも、陽子同士が反発する力(斥力・せきりょく)の方が強くなってしまいます。
原子核は不安定になり、放射線を出して別の安定した原子核に変身する放射性崩壊を起こすわけです。
放射性物質の原子核は、むやみやたらに崩壊するのではありません。
崩壊には、法則性があるのです。
ここに放射性物質が64 gあるとしますよ。
時間Tが経つと、32 gが放射性崩壊を起こして別の物質に変身しました。
さらに時間Tが経つと、残った32 gの放射性物質のうち何gが放射性崩壊を起こすでしょうか?
今度は、残った32 gの半分である16 gの放射性物質が放射性崩壊するのです。
さらに時間Tが経つと、残った16 gの半分の8 gが崩壊します。
原子核は、残った個数の半分が一定時間ごとに崩壊するのですね。
原子核の数が半分になる時間Tのことを半減期と言います。
原子の種類によって、半減期は数日間の場合も数百年~数千年かかる場合もありますよ。
放射線崩壊と半減期について、もう少し詳しく知りたい方は、こちらをお読みくださいね。
放射能と吸収量の単位
放射能の単位は3種類あるのです。
科学者たちが決めたものなので、こういうものなんだ、と覚えてくださいね。
| Bq(ベクレル) | 放射性物質が放射線を出す能力を表す単位 1秒あたりに崩壊する原子核の数のことで[個/s]=[Bq] 1 Bq=1秒間に1個の原子核が崩壊すること |
| Gy(グレイ) | 物質が放射線のエネルギーを吸収した量を表す単位 1 Gy=1 kgの物質が放射線から1 Jのエネルギーを吸収することで[J/kg]=[Gy] |
| Sv(シーベルト) | 人体が受けた放射線からの影響の度合いを表す単位 放射線の種類によって人体への影響の度合いが変わるので、その違いも考慮している |
[Bq]は1秒あたりに崩壊する原子核の数ですね。
つまり、数値が大きいほど放射線を出して崩壊する原子核の数が多いことになりますよ。
物質が放射線をどれだけ受けたのかを表す単位が[Gy]と[Sv]でした。
ですから、同じ1000 [Bq]の放射能でも、放射線の種類やエネルギーの大きさが違ったり、吸収した身体の部位が違えば、人体に与える影響の度合いは違ってくるのです。
こういう人体に与える影響の違いを考慮している単位が[Sv]なんですね。
放射線の性質と利用
放射線には電離作用がありましたね。
放射線が物質を透過するときに、物質中の原子から電子をはじき出してしまいます。
よく「放射線が怖い」と言われますよね。
それは、多量の放射線を浴びると、強い電離作用などによって人間の体内の細胞が壊される恐れがあるからなのです。
ですが、正しい使い方をすれば、色々と有効な利用法があるんですよ。
例えば、人間に役立つ放射線の作用にはこういうものがあります。
- 写真フィルムを感光(かんこう)させる感光作用
- 蛍光(けいこう)物質を光らせる蛍光作用
- 物質に化学変化を起こさせる化学作用
他にも、放射線の性質をうまく使った利用法があるんですよ。
- 非破壊検査:透過力の強いγ線を利用して、金属製品や建物の構造を破壊しないで調べる
- 厚さの測定:β線やγ線が吸収される割合が物質によって違うことを利用している
- 原子力電池:放射線を吸収して熱に変えた後でさらに電気に変える
- 年代測定:\(_{\;{6}}^{14}\rm{C}\)などを使って、半減期から年代を測定する
- 放射線治療:がん病巣にγ線を放射すると正常な細胞より多く損傷することを利用している
- 生物体内の物質の移動:放射性同位体を含んだトレーサーという物質を体内に取り込ませて、物質の移動を調べる
それでは、理解度チェックテストにチャレンジです!
放射線と放射能理解度チェックテスト
【問1】
次の文章中の( )を埋めなさい。
放射線には3種類ある。
(ア)は高速のヘリウム原子核\(_{2}^{4}\rm{He}\)の流れで、(イ)の正電荷を持ち、(ウ)が強くて(エ)が弱い。β線は高速の(オ)の流れで、(ア)より(ウ)が弱く(エ)は強い。(カ)は非常に短い波長を持つ電磁波で、(ウ)は(ア)やβ線より弱いが、(エ)は一番強い。
まとめ
今回は、放射線と放射能についてお話しました。
放射線は、
- 主にα線、β線、γ線の3種類がある
- α線は電離作用が最も強くて透過力が最も弱いが、γ線は電離作用が最も弱くて透過力が最も強い
放射能は、
- 自然に放射線を出す能力のこと
- [Bq]、[Gy]、[Sv]という3種類の単位がある
次回は、放射線崩壊と半減期についてお話しますね。
こちらへどうぞ。