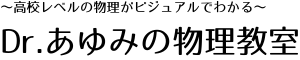世の中のあらゆるものは、『原子(げんし)』というとっても小さい粒々からできています。
私たち人間も、毎日食べているご飯も、机も、パソコンやスマホも、全部この原子が集まったものなんですよ。
自然界にあるものは、一体何からできているんだろう?という疑問は、科学者たちを悩ませてきました。
そして、原子というとても小さな粒々でできている、という結論が出たわけです。
すると今度は、「あらゆるものが原子でできているなら、原子は何でできているんだろう?」という疑問がわいてきたのですね。
大勢の科学者が、長い時間をかけて研究を重ね、色々な原子構造モデルを発表しました。
「原子は陽子(ようし)・中性子(ちゅうせいし)・電子(でんし)からできている」
という話は、学校で習ったり科学の本で読んだりして、知っている人も多いでしょう。
この原子構造が分かってから、実はまだ100年も経っていないんですよ。
そうそう、『原子』と『元素(げんそ)』はごっちゃになりやすいので気をつけましょうね。
『原子』は物質をつくっている小さな粒々のことで、「水素原子」とか「酸素原子」には実体があります。
『元素』は、原子の種類名のことなんですよ。
「水素原子」や「酸素原子」のように、「〇〇原子」の〇〇には原子の種類名が入りますね。
この〇〇が『元素』なんです。
それでは、科学者たちがようやく解き明かした「原子の構造」について、詳しく見ていきましょう。
※スマートフォンで表が全て見られない場合は、横スクロールしてください。
目次
原子
原子の構造
原子の構造はこんなイメージなんです。

図1 原子の構造
中心にある赤い●を原子核(げんしかく)、その周りの軌道(きどう)をぐるぐるまわっている青い●を電子と言います。
原子核はプラスの電荷(正電荷・せいでんか)を持っていて、電子はマイナスの電荷(負電荷・ふでんか)を持っているんですね。
さて、原子や原子核の大きさって想像がつきますか?
原子の大きさとは、電子が飛んでいる軌道の直径のことですよ。
一番小さい水素原子の直径は10-10 mくらいで、原子核の直径は10-15 mくらいだそうです。
大きさが10万倍くらい違いますね!
原子核が直径1 cmの円だとすると、原子は直径1 kmの円になります。
野球場が原子だとしたら、その中心に置いた米粒が原子核にあたるでしょうか。
原子の中って、スカスカなんですね。
次は、原子核の中を見ていきましょう。
原子核をつくる陽子と中性子
原子核は、陽子と中性子という2種類の粒子が集まってできています。
- 陽子:正電荷+e [C]を持つ
- 中性子:電荷を持たない中性の粒子
[C]は電気量の単位でクーロンと読みますよ。
陽子は正電荷を持っていますが、中性子は電荷を持っていません。
ですから、原子核(陽子+中性子)は正電荷を持っているわけですね。
陽子と中性子をまとめて、原子「核」をつくる粒「子」である核子(かくし)と言います。
原子核の中はこんなイメージです。

図2 原子核と陽子と中性子
陽子は正電荷を持っているのでした。
同じ正電荷を持っているなら、陽子が2個以上あると斥力(せきりょく)という静電気力(せいでんきりょく)が働いて、反発し合うはずですよね。
反発したら、原子核としてまとまっていられません。
どうして反発せずにくっついていられるのでしょう?
それは、中性子のおかげで核子(陽子と中性子)の間に強い引力が働くからなんですよ。
この核子間に働いている引力を、核力(かくりょく)と言います。
さあ、原子をつくっている陽子・中性子・電子が出そろいました。
その関係をまとめておきましょう。
陽子と中性子と電子の関係
電子について、ちょっとつけ加えておきますよ。
負電荷-e [C]を持つ電子の数と、正電荷+e [C]を持つ陽子の数は同じです。
つまり、原子の中で正電荷と負電荷が打ち消し合いますね。
ですから、原子は電気的に中性になるわけです。
また、電子の質量はとても軽くて、陽子の質量の約1/1840になるそうです。
(陽子と中性子はほぼ同じ質量です)
陽子や中性子と比べて、無視できるくらいの質量なんですね。
陽子・中性子・電子の関係を表にまとめました。
| 電気量(電荷) | 質量 | ||
| 原子核 | 陽子 | +e [C] | ほぼ等しい |
| 中性子 | 0 | ||
| 電子 | -e [C] | 陽子や中性子の1/1840 | |
ところで、現在確認されている原子の種類(元素)は118種類で、自然界に存在するものは92種類あるんですね。
1つ1つ区別できるようにそれぞれ番号がついていて、その番号を『原子番号』と言うんですよ。
周期表でもおなじみですよね。
原子番号をどうやって決めているのか、知りたくありませんか?
原子番号と中性子数と質量数の関係
原子核の中にある陽子数は元素によって違うのです。
つまり、陽子数が元素としての性質を決めているわけですね。
その陽子数を原子番号と言い、Z(数や番号を表すドイツ語Zahlに由来)で表します。
原子番号Zの原子はZ個の陽子を持っています。
ですから、原子核はZe [C]の正電荷を持っているわけですね。
そして、原子番号と同数のZ個の電子が原子核の周りをまわっています。
さらに、核子である陽子と中性子の数を合わせて質量数と言い、A(原子質量数を表すドイツ語Atommassenzahlに由来)で表します。
原子番号(陽子数)をZ、中性子数をN(中性子数”neutron number”に由来)、質量数をAとすると、
A=Z+N
という関係になるわけです。
あれ、電子数が入っていませんよ。
電子の質量は、陽子や中性子に比べて無視できるくらい小さいのでしたね。
ですから、質量数に電子数は含まれないのです。
それから、質量数に単位はありません!
これも覚えておいてくださいね。
また、原子核の構成は、元素記号X、原子番号(陽子数)Z、質量数Aを使って、
\(_{Z}^{A}\rm{X}\)
と表すことが決められていますよ。
原子番号20までは覚えておいてくださいね。
では、原子番号2のヘリウムHeを使って、学んだことをまとめておきましょう。

さて、原子の構造について基本的な話をもう少ししておきますね。
原子番号は同じだけど質量数が違う、という兄弟のような存在がいるのです。
同位体
原子番号(陽子数)Zは同じでも質量数Aが違う、という原子のお話をします。
質量数だけが違う、ってどういうことでしょう?
質量数A=原子番号Z+中性子数Nですから、中性子数Nが違うのですね。
このような原子を同位体(どういたい)またはアイソトープと言います。
例えば、水素Hの同位体を見てみましょうか。
天然には3つの同位体があるんですよ。
 |
 |
 |
| 水素 \(_{1}^{1}\rm{H}\) 陽子数1、中性子数0 |
重水素 \(_{1}^{2}\rm{H}\) 陽子数1、中性子数1 |
三重水素 \(_{1}^{3}\rm{H}\) 陽子数1、中性子数2 |
| 99.9 % | 0.1 % | ごく微量 |
どれも原子番号1の水素炭素Hですが、中性子数が違うので質量数が違いますね。
なので、同位体の関係にあるわけです。
また、同位体によって存在比が違っているんですよ。
普通の水素が一番多くて99.9 %、重水素が0.1 %、三重水素はほとんど存在しないのです。
同位体の原子番号(陽子数)は同じですから、原子番号と同数の電子数も変わりません。
つまり、電子配置が変わらないので、同位体の化学的性質は同じなんですよ。
化学的性質とは、電気陰性度(陰イオンへのなりやすさ)やイオンの価数など電子数に関係する性質のことですね。
(ちなみに、物理的性質とは質量とか融点、沸点、比重などで質量数が関係します。ですから、同位体の物理的性質は違ってきます)
では、理解度チェックテストにチャレンジしましょう!
原子の構造理解度チェックテスト
【問1】
次の文章中の( )を埋めなさい。
①原子は(ア)と負電荷を持つ(イ)からできている。(ア)は正電荷をもつ(ウ)と電荷を持たない(エ)からなる。(ア)を構成する(ウ)と(エ)を合わせて(オ)と言う。(オ)同士を結びつける力を(カ)と言う。
②(ア)に含まれる(ウ)の数は元素によって異なり、その数を(キ)と言う。また、(ウ)の数と(エ)の数の和を(ク)と言う。原子番号4の原子の(ア)は(ケ)の正電荷を持つ。
③(ウ)数Zは同じだが(エ)数Nが変わるために質量数Aが違う(ア)を持つ原子を(コ)と言う。(コ)では(イ)配置は同じなので、原子の(サ)は変わらない。
【問2】
次にあげる原子の原子番号、陽子数、中性子数、電子数、質量数を答えよ。
(1)\(^{12}\rm{C}\) (2)\(^{13}\rm{C}\) (3)\(^{18}\rm{O}\) (4)\(^{35}\rm{Cl}\)
まとめ
今回は、原子の構造についてお話しました。
原子の構造は、
- 正電荷を持つ原子核と負電荷を持つ電荷でできている
- 原子核は陽子と中性子からできており、まとめて核子と言う
- 原子番号Z、中性子数N、質量数Aの関係は、A=Z+N
- 原子核の構成は、元素記号X、原子番号Z、質量数Aを使って、\(_{Z}^{A}{X}\)
同位体とは、
- 原子番号が同じで質量数が違う原子
- 電子配置が変わらないので、原子の化学的性質は変わらない
次回は、放射線と放射能についてお話しますね。
こちらへどうぞ。