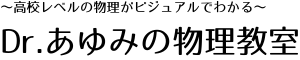『熱力学第1法則』のポイントの一つが、「熱の一部を仕事に変えることができる」ということでしたね。
この発見が、人間の生活を大きく発展させたのです。
熱が生み出す仕事は、人間に比べて圧倒的なパワーがあったのですね。
ですから、科学者たちは熱を仕事に変える装置である『熱機関(ねつきかん)』の技術を懸命に研究・開発しました。
そのおかげで、人間が重労働をしなくても、重い物を運んだりたくさんの製品を作ったりできるようになったわけですね。
分かりやすい例が、歴史の授業で出てきますよ。
18世紀後半に起こった産業革命です。
さて、産業革命と言えば必ず出てくる装置がありませんか?
そう、「蒸気機関」です。
石炭を燃やした熱で発生した蒸気を使ってものを動かす蒸気機関は、『熱機関』の一つなんですよ。
身の周りにある代表的な熱機関を挙げてみましょうか。
- 蒸気機関車
- 自動車などのガソリンエンジン
- トラックや船舶などのディーゼルエンジン
- 発電所の蒸気タービン
などがありますよ。
熱機関のおかげで快適な生活ができていることが良く分かりますね。
では、生活に欠かせない熱機関の仕組みについて、詳しく見ていきましょう。
目次
熱機関と熱効率
熱機関とその仕組み
『熱機関』とは、熱を仕事に変える装置のことでした。
物理学的に言うと、「高温の熱源から熱量を得て、仕事をし、仕事に変えられず余った熱量を低温の熱源(大気中)へ排出する装置」となるのですね。
図にすると、こうなります。

図1 熱機関の仕組み
具体的な例を見てみましょうか。
蒸気機関車の仕組みを簡単な図にしてみました。

図2 蒸気機関車の仕組み
石炭を燃やして熱を発生させる(高温熱源)
↓
熱によってお湯を沸かして蒸気を発生させ、蒸気でピストンを押し、車輪を回転させる(仕事)
↓
ピストンが元に戻るときに蒸気を大気中(低温熱源)に放出する
という仕組みになっているんですね。
これを繰り返して車輪を回転させ続けるわけです。
ガソリンエンジンやディーゼルエンジンはもっと複雑ですが、基本的には、
燃料を燃やして熱を発生させる(高温熱源)
↓
熱によって気体を膨張させてピストンを押し、クランク軸を回転させる(仕事)
↓
ピストンが元に戻るときに排気ガスを大気中(低温熱源)に放出する
という仕組みになっているんですよ。
というわけで、『熱機関』は吸収した熱量を仕事に変える装置でした。
吸収した熱量のうちどれくらいの量を仕事に変えられるのでしょうね?
熱効率とは?
もちろん、昔の科学者たちも、吸収した熱量のうち仕事に変えられるのはどれくらいか?を知りたいと思っていました。
そこで、熱機関が高温熱源から得た熱量の何%を仕事に変えられるかという割合を『熱効率(ねつこうりつ)』と呼ぶことと、その計算方法を決めたのです。
『熱効率』は『熱機関の効率』とも言いますよ。
例えば、お母さんが子どもに買い物を頼んだとしましょう。
「この3000円を持って、スーパーでお肉を買ってきてくれる?」
ところが、スーパーには欲しいゲームと漫画が売っていたのです。
ついつい2000円を無駄遣いしてしまいました!
そして、買ってきたのは残った1000円で買えるお肉でした…。
子どもは、もらったお金の1/3の仕事しかしてくれなかったわけですね。
この話と熱効率は同じことなんですよ。
では、熱効率の計算方法を見てみましょう。
熱効率の公式
ある熱機関が、高温熱源からQin [J](ジュール)の熱量を吸収して仕事W [J](Wは仕事”work”に由来)をしています。
その時、外部の大気中(低温熱源)にQout [J](Qは熱量”quantity of heat”に由来)の熱量を放出してしまいました。
図にすると、こんな感じですね。

図3 熱機関の仕組み
熱効率は、高温熱源から得た熱量Qinの何%を仕事Wに変えられるかという割合でしたね。
ですから、熱効率e(効率”efficiency”に由来)を求める式はこうなりますよ。
e=W/Qin
また、W=Qin―Qoutですから、
e=(Qin―Qout)/Qin
=1―Qout/Qin
と表すこともできますね。
ところで、熱効率eの値の範囲はどれくらいなのでしょうか?
熱効率の値の範囲
eの値の範囲は、
0<e<1
となります。
e=0にならない理由は簡単です。
e=0ということは、W=0(Qin=Qout)、つまり、仕事をしていないわけです。
仕事をしない熱機関は、熱機関ではありませんね。
では、e=1とならないのはなぜでしょうか?
e=1ということは、W=Qin(Qout=0)、つまり、吸収した熱量が全て仕事に変わります。
熱効率100%というわけで、理想的ですよね。
なので、科学者たちは研究を重ねたのです。
そして、理論的に「W=Qin(Qout=0)になるのは、外部の大気(低温熱源)が絶対零度になるとき」ということが分かりました。
外部の大気が0 Kって、あり得ませんよね。
-273.15 ℃なんて、寒すぎ!!
ですから、必ずQout>0となります。
そうするとW<Qin、つまり、e<1となるわけです。
それに、現実の熱機関ではどうしても色々なエネルギー損失が発生してしまいます。
例えば、ピストンが摩擦する熱エネルギーとかエンジンがうなる音のエネルギーとか。
その分、仕事に変えることはできなくなりますね。
というわけで、とても残念なお知らせです。
熱機関は吸収した熱量全てを仕事に変えることはできません。
熱効率100 %の熱機関は存在しないのですね。
とは言っても、100 %ではなくて良いから、熱効率の値が大きい熱機関が欲しくなりますよね。
では、実際の熱機関の熱効率はどれくらいなのでしょうか?
実際の熱効率はどれくらい?
世の中にある熱機関の熱効率は、これくらいです。
| 熱機関 | 熱効率 |
| 蒸気機関 | 0.1~0.2 |
| ガソリンエンジン | 0.2~0.3 |
| ディーゼルエンジン | 0.3~0.4 |
吸収した熱量の10 %~40 %が仕事に変えられているのですね。
燃料の種類やエンジンの構造を工夫したり、熱効率を上げる努力は今も続けられているんですよ。
では、例題を解いて理解を深めましょう。
例題で理解!
ガソリンの燃焼熱は1.0 gあたり5.0×104 Jとして、次の問いに答えよ。
(1)1時間の燃焼熱は何Jになるか。
(2)ガソリンエンジンが1時間にする仕事量は何Jになるか。
(1)ガソリンの燃焼熱は1.0 gあたり5.0×104 Jです。
1時間あたりに500 gのガソリンを消費するので、1時間の燃焼熱は、
5.0×104×500=2.5×107 J
(2)仕事量=仕事率×時間[秒]ですから、1時間にする仕事量は、
500×60×60=1.8×106 J
では、理解度チェックテストにチャレンジしてみましょう!
熱機関と熱効率理解度チェックテスト
【問1】
毎秒500 Jの熱を吸収して200 Jの仕事をする熱機関の効率を求め、%で答えよ。
【問2】
ある熱機関の最大仕事率は500 kW(キロワット)である。この熱機関が最大仕事率で1.0時間運転するには、燃料が何kg必要か求めよ。
ただし、燃料1.0 kgの発熱量を5.0×107 J、熱機関の効率を0.30とする。
まとめ
今回は、熱機関の例と熱効率の計算方法についてお話しました。
熱機関とは、
- 熱を仕事に変える装置
熱効率とは、
- 熱機関が高温熱源から得た熱量の何%を仕事に変換できるかという割合
- 熱機関が高温熱源からQin [J]の熱量を吸収して仕事W [J]を行い、外部の大気中(低温熱源)にQout [J]の熱量を放出したときの熱効率eは、
e=W/Qin=1―Qout/Qin (0<e<1)
熱効率の求め方は、意外と簡単でしょう?
QinとQoutを間違えないようにしてくださいね。