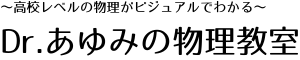これまでは『物体の運動』について学んできましたが、ここからは、運動のもととなる『力』について学んでいきましょう!
さて、そもそも『力』って何なのでしょうか?
物理学なので、筋力や能力じゃないな・・・ということは分かりますね。
例えば、ばねに力を加えると、ビヨーンと伸び縮みします。
止まっている台車を力をこめて押すと、ゴロゴロ動きだしたり向きが変わりますよ。
このように、力が物体に働くと、物体が変形したり動き出したりしますね。
つまり、力は世の中の全ての物体に関係しているんです。
なので、色々な現象が起こる原因を探るために、色々な力の働きを考えるわけですね。
物理学は、『力』について考える学問でもあるんですよ。
で、この先は公式の丸暗記が通用しません!
物体にどんな力がどのように働いているか自分で見つけて考えないと、公式の使いようがないんですよ。
では、力とは何か、力の単位、力の表し方の順にお話していきますね。
目次
力とは
力の定義
物理学では、『力』はこのように定義されていますよ。
- 物体を変形させる原因となるもの
- 物体の運動状態を変化させる原因となるもの
1.にあたるものには、ばねの伸び縮みがありますね。
複雑になることが多いので、高校物理ではばね以外は取り上げません。
2.の「運動状態を変える」と言うのは、速度や向きを変化させるということです。
高校物理で良く出てくるのはこちらの方ですね。
さて、物理で取り上げる『力』には、どんなものがあるのでしょう?
力の種類
力を大きく分けると、重力(じゅうりょく)、接触力(せっしょくりょく)、慣性力(かんせいりょく)、静電気力(せいでんきりょく)、磁気力(じきりょく)の5種類になりますよ。
力学分野の物理基礎編では、『重力』と『接触力』だけを考えていきますね。
『重力』は、地球上のあらゆる物体が地球から下向きに受けている引力ですね。
私たちの身体や物体が床の上で静止していても、落下していても、水にプカプカ浮いていても重力を受けているんですよ。
目の前のボールペンを持ち上げてから離すと、重力を受けて地球に向かって落ちていきますね。
物体は、地球にくっついておらず空中にあっても重力を受けているんです。
重力は、地球がつくり上げた重力場という空間から受ける力で「場の力」のひとつなんですよ。
それでは、『接触力』とは何でしょうか?
これは、重力とは違って、物体が他の物体と直に接触している点から受ける力なんです。
例えば、あなたが床の上に立っている、つまり、床に接触しているとしましょう。
あなたの体重で床を押すので、あなたは床が押し返す力を受けていますよ。
そうでなければ、床が抜けちゃいますね。
これが『接触力』の例ですよ。

図1 重力と接触力
接触力には、次の5つがあります。
- 床などの面が押し返す垂直抗力(すいちょくこうりょく)
- 糸やひもが引っ張る張力(ちょうりょく)
- ばねやゴムがもとに戻ろうとする弾性力(だんせいりょく)
- 粗い面からこすられる摩擦力(まさつりょく)
- 液体や気体から受ける上向きの浮力(ふりょく)
それぞれの力については、これから順番に学んでいきますよ。
この先も「物体に働く力」や「物体が受ける力」という表現が出てきますが、どちらも同じことを言っています。
物体に働く力=物体が受ける力、つまり、力は全て受け身で考えるんですよ。
ところで、物理量にはm(メートル)やkg(キログラム)など色々な単位がありますが、力の単位ってあるのでしょうか?
力の単位はニュートン
力の単位の定義
力の大きさを表す単位は[N](ニュートン)が使われますよ。
あの有名なイギリスの科学者アイザック・ニュートンにちなんでつけられました。
定義は、ちょっと分かりにくいかもしれませんね。
- 質量1.0 kgの物体に作用して1.0 m/s2(メートル毎秒毎秒)の加速度を生じさせる力が1.0 N
後から運動方程式のところで、質量m [kg](質量”mass”の頭文字)の物体に力F [N](力”force”の頭文字)を加えると速度が変化して加速度a [m/s2](加速度”acceleration”の頭文字)が生じることを表した式F=maについて学びます。

図2 物体に力を加えると物体は加速する
この式に質量m=1.0 kg、加速度a=1.0 m/s2を代入したときの力がF=1.0 Nということなのです。
つまり、1.0 N=1.0 kg・m/s2なんですね。
では、この力の単位の定義を頭に入れて、重力について考えていきますよ。
重力は何ニュートン?
地球上のあらゆる物体は、地球に引っ張られる重力を受けていますね。
重力の大きさは、物体によって違うんですよ。
物体の質量が大きいほど、受ける重力は大きくなるんです。
物体が落下するときの加速度は、重力加速度g=9.8 m/s2(gは重力”gravity”の頭文字)でしたね。
なので、質量1.0 kgの物体が受ける重力は、1.0 kg×9.8 m/s2=9.8 Nとなります。
そうすると、質量2.0 kgの物体が受ける重力は、2.0×9.8 Nですね。
もう少し物理学っぽい書き方にすると、「物体が受ける重力の大きさW [N]は、比例定数を重力加速度g [m/s2]として、物体の質量m [kg]に比例する」というわけです。
つまり、質量m [kg]の物体が受ける重力W=m [kg]×g [m/s2]=mg [N]
この数式から、物体が受ける重力W(重量”weight”の頭文字)の大きさが計算できますよ。
これからも使う重要な式なので、必ず覚えましょう!
さて、重力には大きさだけでなく向きもありますね。
地球に引っ張られる力なので、物体が受ける重力は下向きの力です。
机の上のペンを持ち上げてみてください。
ペンは重力を受けますが、あなたが持ち上げた上向きの力も受けているから落っこちませんね。
つまり、力は大きさと向きを持っている量=ベクトル量です。
なので、矢印で書くことができますよ。
力を矢印で書くと、どこからどの向きにどのくらいの大きさの力が働いているか、はっきり分かって便利なんですね。
では、矢印を使った力の表し方を見ていきましょう!
力の表し方と力の3要素
力は大きさと向きを持つ量(ベクトル)なので、矢印を使って表します。
力の大きさは矢印の長さ、力の向きは矢印の向きとなるわけですね。
力が働く点は矢印の始点となり、この点を『作用点(さようてん)』と言います。
この矢印を延長した線を『作用線(さようせん)』と言いますよ。

図3 力の表し方
力の矢印の「大きさ・向き・作用点」のことを『力の3要素』と呼びます。
例えば、物体にひもをつけて右に引っ張るときの張力を書くと、こんな感じです。

図4 物体をひもで引っ張るときの張力
色々な力の具体的な書き方は、それぞれの力について解説した記事の中で話しますね。
仕上げに、理解度チェックテストにチャレンジしましょう!
力の種類と単位・力の3要素理解度チェックテスト
【問1】
次の文章中の( )内を適切な言葉で埋めよ。
(1)物理学では、力は次のように定義されている。
- 物体を(ア)させる原因となるもの
- 物体の(イ)を(ウ)させる原因となるもの
(2)力の大きさを表す単位は(エ)と言い、アルファベットの(オ)で表す。
【問2】
次の文章中の( )内を適切な言葉で埋めよ。
力は(ア)と(イ)を持つベクトル量なので、(ウ)を使って表せる。
矢印の長さは力の(ア)、矢印の向きは力の(イ)、矢印の始点は力が働く(エ)である。
この矢印を延長した線を(オ)と言う。
力の矢印の(ア)・(イ)・(エ)のことを力の(カ)と言う。
まとめ
今回は、力の種類と単位や力の3要素についてお話しました。
物体に働く力は、
- 『重力』と『接触力』があり、『接触力』には張力、垂直抗力、摩擦力、弾性力、浮力の5つがある
力の大きさの単位は、
- [N](ニュートン)であり、1.0 Nは質量1.0 kgの物体に作用して1.0 m/s2の加速度を生じさせる力
質量m [kg]の物体が受ける重力W [N]の大きさは、
- W=mg(g:重力加速度)となる
力の3要素とは、
- 物力を表す矢印の大きさ・向き・作用点のこと
これから色々な力について学んでいく上で、最も基本となる内容でしたね。
ここでしっかりと頭に入れておきましょう。
次回は、力の合成と分解、力のつり合いについてお話しますね。
こちらへどうぞ。